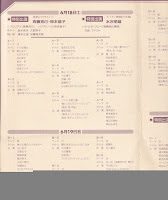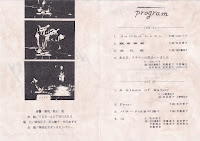高校の頃に最初に書いた小説『家庭』というタイトルを、『家と庭』と変更して、その過去を現在と将来に投機的に融合させて書き直してみるのが、余生の作業になるだろうと、考えはじめだしていた。しかし、自分ひとりでは見通しがつかないので、何かに出会えないかな、とおもっていた矢先、まず図書館で、一冊目に出会う。千葉市の中央図書館で本を借りてから、ぶらっと、館員が選んだ新書購入の棚に目配りしながら素通りしようとしたら、『家の哲学』というタイトルが目に飛び込んできて、そのまま借りた。その帰り、千葉駅ビルの上階にあるくまざわ書店に立ち寄ってみたら、こんどは『庭の話』という本が積み上げられているのに出会い、購入してきた。
一方は、「家」といい、もう一方は、「庭」という。しかしどちらも、似たようなことを言っているような気がする。用語が違うのは、おそらく、文化的なバイアスと、まず意識しなくてならないその文脈(誰に向かってまず話すか)、なんではないかと思う。考察しようとしている現状の認識は同じに近いだろう。一方は、その行き詰まりを「庭」的といって「家」を志向し、もう一方は「家」的と批判して「庭」を志向している。が、その打開策に必要な思考転換のキー概念として、家の中や庭に訪れる様々な事物や多種他生物とのアニミズム的な交換、身体の変容といった観点を導入しているのだ。
どちらにも、フランスの庭師、「動いている庭」を提唱したジル・クレマンへの言及がある。
そこを引用して指摘しよう。長くなるが。
<森を家の事柄へと変容させることは、家の経験を別の視点から改変することも意味している。木々がこのように領域を侵犯してくるように表れてきたことで、バルコニーには、それまでミラノで見たことのなかった、虫と鳥の半獣神が住むことになる。あたかもわたしたちと異なる種へと住まいが開かれていることによって、居住可能な空間、あるいは生態系の観念そのものが爆発したかのようだ。わたしが木々にアパートを開くと、木々は彼らの家を鳥と虫たちに開いたのだ。ある種が現前しても、他の種が追いやられることにはもうならない。ある種が住みつくことによって、他の種が来て定住することが可能になる。家は多種がもつれあう装置となる。各々の種の家は、他の種の身体である。したがって、あらゆる家は、つねに他者たちの家であり、他の生きものたちがすでに占拠していた空間なのだ。
このような家空間の観念的革命が、わたしたち木々との関係を再定義することによって可能となるというのは、偶然のことではない。住居はつねに街に関連づけられてきたわけではない。長らく、自分の家にいることは、街に暮らすことや、街に定住したいということとは同義でなかった。住居はノマドであり、旅することができ、石材よりも動物に由来する材料で建てられることの方が多かった。家を都会的で、安定した、土地に定着した、それゆえ無機質なものとしてきたのは、庭である。人類が自分の運命を木々や、ある場所に現れた多年生の植物と結びつけることを決めたとき、住居は旅をやめ、あらゆる植物とまったく同じように、領域に固定された。ある意味で、都会のあらゆる住居、動かない安定的な場所としてのそれは、植物的な思い上がりのようなものに属すると言いうることになる。(略)
庭によって、それゆえ農業によって、街に住居をつかまえておくことができるようになったという考えは、長らく人類にとって重要だった。(略)「都会の革命」は農業であり、食料を同じ場所に長期間たくわえ、保存する可能性がもたらしたものにほかならない。街は庭から発生したものである。
この洞察――もっと最近では、ジル・クレマンによってふたたび主張された洞察――を真面目に受け取るならば、変様するのは家の観念そのものだ。実際には、わたしたちの住む家は根本的に、多種的なプロジェクトである。植物と木々がある場所にしか、住居は存在することができない。反対に、わたしたちが客間で育てる観葉植物は、街の外に存在する植物を想起させるのではなく、わたしたちの家が、植物の生活形式と結びついたために動くのをやめたという事実を明らかにするのである。植物への愛によって、わたしたちはノマド主義と手を切ることができたし、庭への執着によって、自分の住居を街として組織することができた。庭は都会という組織の反対物ではない――その本来の核なのだ。>(『家の哲学』「庭と森」)
このコッチャの言い回しを、正確に理解できているのか不安なのだが、わたしなりにこの「家と庭」(という小説という形)をめざすブログの文脈で要約すれば、こういうことだ。動いてきた植物を愛し、執着することによって、人は定住した、そのかわり、失われたノマドな郷愁的な本能を、家の中に動きを取り入れることで、つまり家の考えを変容させることで、家が単なる囲いではなく多事物と他生物とのアニミズムな交換=交感あふれる豊な場所に変えていく実践が行なわれたのだ。だからそう人を動くように仕向けたのは、<動かない庭>だった、と。
たぶんなのだが、イタリア人のコッチャが「家」と言いたがるのは、「オイコス(家政)」という概念の豊かさを回復させたい西洋哲学的な文脈(伝統)があるからなのではないか、とおもう。宇野常寛も、「庭」という概念を検討するさい、gardenやyard、courtといった西洋の概念と日本の古語的意味を対比させている。西洋的には、庭、というと、囲われた園(外と内をわけたもの)、というニュアンスが強く、日本の古語では、それらが分けられていない能動的な場所なのである(が、日本の近代造園学会ではこの古語の意味が無視されてきて、まったくもって西洋概念一辺倒で狭くさせられて、ランドスケープ造園とやらが、ゼネコン的に実地・現場も支配している)。だから西洋概念では、庭という言葉が狭く、オイコスの連想を維持する家という言葉の方が、広いのではないかと推察する。(が、ヘブライ語で、「エデン」という語が、日本の庭の古語に近い両義性としてあるようである、と、大澤真幸の「世界史の哲学」だかに言及があったと記憶する。)
が、だとしても、つまりどちら両者の更新概念の意図は重なり似ている提唱だとしても、そこから実践へ向けての提議となると、だいぶ変わってくることになっているのかもしれない。とくにコッチャは、訳者の後書きの言及でもあるように、上で引用した箇所ではネガティブだった「石(材)」への評価が、あとから高くなってきているのだ(やはり石の文化なのか?)。それは、錬金術の歴史を喚起させながら、石がPCやスマホといった「賢者の石」に変容していったことと重ねられるのだ。コッチャは、庭と対立する概念として、料理(錬金術)をする「台所」をあげる。
<家は将来、集団的な混合の規範となる。それは、階級の混合であり、アイデンティティの混合であり、人民の混合であり、文化の混合である。家はつねに、世界の台所である。家によってこそ、地球は新たな味を見つけることになるであろう。>(「結論 新しい家、あるいは賢者の石」)
ここでの「地球」とは、土でできたものではなく、あくまで石でできたものとして観念されている。が前提として、「台所」(料理)を、ニュートンの古典物理学ではなく、量子力学の新物理学で更新させようとしている。ここでの「石」とは、物質的というより、波的なもの、重なりやもつれとして料理(錬金)されうる、と理解を深めようとしている。が具体的には、ではその「新しい家」へ向けてどうするのかまでは提示していないのでわからない。
ので、とりあえず、わたしは、そのコッチャの実践提案に、否定的な立場をとる。それは、現今の、バイオテクノロジーや量子コンピューター開発、宇宙開発へと結びついてゆく発想ではないかと勘繰るからだ。それは、外へと移動していくロマンチックなノマド志向だ。それは、無際限という意味での無限にすぎない。俗にいえば、性懲りもなく、ということだ。世界を支配するプラットフォーマーたちは、地球が飽和してしまったので、こんどはプラネットフォーマーになろうと宇宙という外へ飛び出していこうとしている。胡散臭い。
が、日本での、庭という古語概念に立ち返って思考を更新させていこうとする宇野は、ちがう実践を提起しているようだ。彼も、地球としての庭、を射程に据える。が、それは、無際限としての地球(宇宙)ではなく、<実無限>としての地球(宇宙)であある。世界は閉じられた、外はない、しかしそれは、無限が実在することを教えてくれるのだ。この<実無限>という用語は、柄谷の『探求』を思考の下敷きに引いたような宇野の著作を読んでいて思い出した、柄谷の『探求』からの借用である。たしか、カントールの集合論での概念で、それを、経済グローバリズムと、庭における借景や縮景の技術と結びつけて論考していたはずだ。三十年前に書いた『庭へ向けて』で引用してある。
次は、あらためて、宇野常寛の『庭の話』について、おもいめぐらした考えをメモしよう。